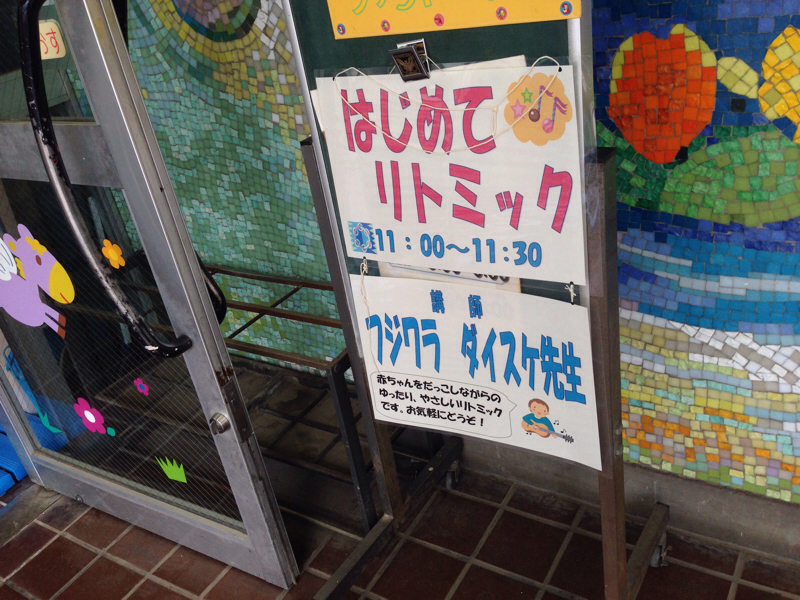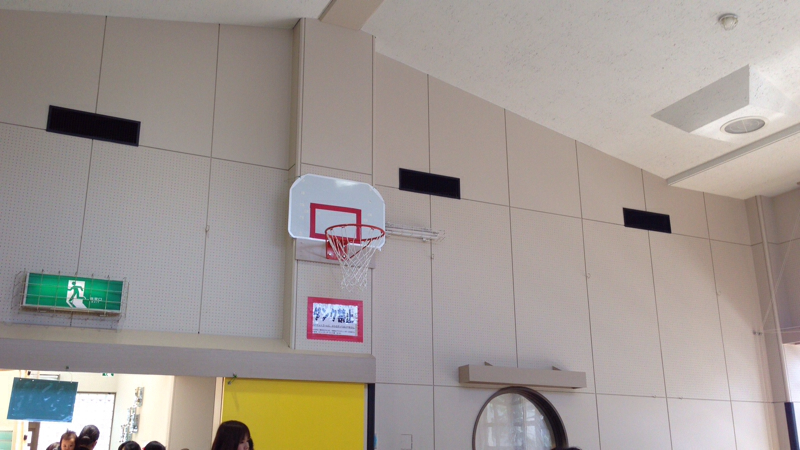活動で使う楽器や、方法を工夫すれば2歳児前後の親子グループでも「合奏」の形をとることができます。
どんな楽器を使うとよい??
それぞれの楽器が異なる種類の音の方が鳴らしている「自分の音」を意識しやすくなります。
上記の写真では2種類の楽器。
「キンキン」と金物系の音であるベルと「シャカシャカ」といった乾いた音のマラカスです。
言葉で伝える際にも「カラカラ」「リンリン」など擬音でイメージを伝えやすくなります。
2歳前後の子どもを考えると、鳴らす楽器は「振る」「たたく」といった簡単に演奏できるものがよいでしょう。
ハンドベル
エッグシェーカー
グループに分かれて「合奏」の形を設定する。
二種類の楽器を使うとします。
すると2グループに分かれることになりますが、この時ちょっと大変ですが参加者に移動してもらって二手に分かれるかたちになってもらうようにします。
こうすることで、子どもから見ても「自分側」と「あっち側」が見えやすくなります。
このまま一斉に全員に楽器を配って自由に(または何か音楽をいっしょに)鳴らす形が、一番かんたんな合奏の形です。
例えば、歌の中でセクションごとで、鳴らすパートを分けるなど発展も可能です。
しかし、基本的に子どもは手に楽器を持ち続けると「止めておく」ということは難しいので(楽しくて鳴らし続ける)、一回では無理でしょう。
合奏とはいえ、「完璧に」行う必要はありません。
「親子で一緒にできた」という経験にフォーカスしていくと、活動が意味を持ってきます。
[cc id=3452]