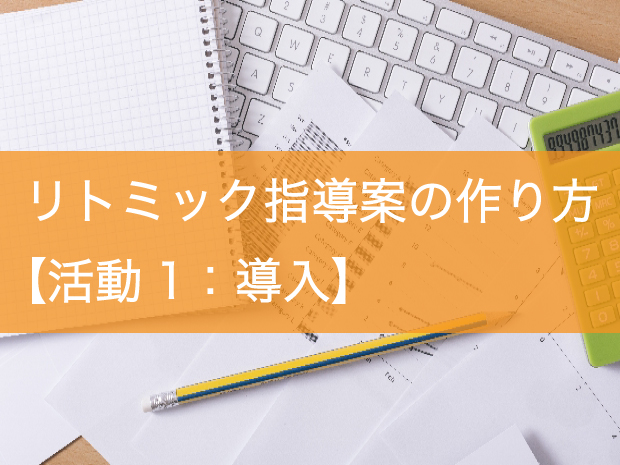
リトミック指導案の作り方、サンプル指導案をもとにご説明いたします。
ここまで、『指導案の組み立て方」の基礎部分についてお話をいたしました。
→リトミック指導案の作り方 その1 【スムーズな活動にするための全体構成の仕方】
今回からは資料として指導案を用意しました。これをもとに「なぜこの活動を行うのか?」といったことをご説明していきます。
もちろん、これは私のやり方というだけで正解ではありません。
あくまで参考程度にとらえていただけると幸いです。
最初に行うべきことは「緊張をほぐす」こと
今回のサンプル指導案では「初回」ということを想定しています。
初回の場合、子ども達がこちらに向けるものとして「興味」と「不安」があります。
もし、普段から子ども達と関わりがある中で「初めてのリトミック」というのであれば「先生、なにするんだろ!?」と「興味」の方が優っているでしょう。
しかし、子ども達とは初対面で関係がまだ作られていない場合は「不安」方が勝ることが多いです。
それなので、この導入部分は
簡単なことから始めていくと、子どもも入ってきやすい
いきなり「さあ!お散歩で!歩くよ!」なんて大きい活動は警戒されるので行えません。
とても簡単なことから始めていくようにします。
活動:∇手で膝など身体の部位を鳴らし続ける~止める
この活動は、子ども達が座っている対面の位置(1~1.5メートルくらい離れる)に指導者も座り、「同じ目線で、接近し過ぎない距離」から関係を作っていくようにしています。
「先生の真似っこしてね」と伝え手を鳴らし続けます。
ある程度の子達がのってきたら、おもむろに手を止めるようにします。子ども達が「!?」と手を止めたら、「先生が止めたら、みんなも”ピタッ”と止めてみてね」と伝えます。
この段階で「真似をして鳴らす→止める」のルールが提示されました。
一回で全員が理解することはないので、その後何回か繰り返しましょう。
しかしこれだけでは、子どもからすると「単にやらされているだけ」になってしまいます。
8割位の子が出来るようになってきたら、止めるタイミングを変えていくようにします。
パターンを揺らしていくことで「遊び」や「ゲーム」感覚になってきます。
次第に子ども達は「次はいつ止まるんだろう!?」と期待して手を止めていこうとするので自発的なものになっていきます。
この段階から「目標」へのアプローチは始まっている
今回の指導案、大きな目標として「音の有無への即時反応」とあります。
この活動の段階では「音に合わせることを意識する」という小目標で行っていますが、実際は大きい目標である「音の有無」にも繋げています。
それなので、一つの目標は一つの活動で達成を目指すわけではありません。
物事を身につけるには、一回ではなく繰り返し経験することが大切です。
それなので、
次回は、 もう一歩進めた導入部分についてです。
リトミック指導案作成に役立つ本
| おすすめ本 | 詳細 |
|---|---|
 |
リトミック教育のための原理と指針 ダルクローズのリトミック リトミックの理論やアプローチ方などわかりやすく解説された名著です! |
 |
リトミック論文集 リズムと音楽と教育 エミールジャック=ダルクローズ ダルクローズの論文集。難解な本ですが、読めば読むほど彼の想いや意図が身に染みます。 |
 |
子供を動かす法則 (教育新書 41) リトミックの本ではありませんが、子どもに教えるために必要な技術が網羅されています。リトミック指導者こそ読んでおくべき必読書。 |
