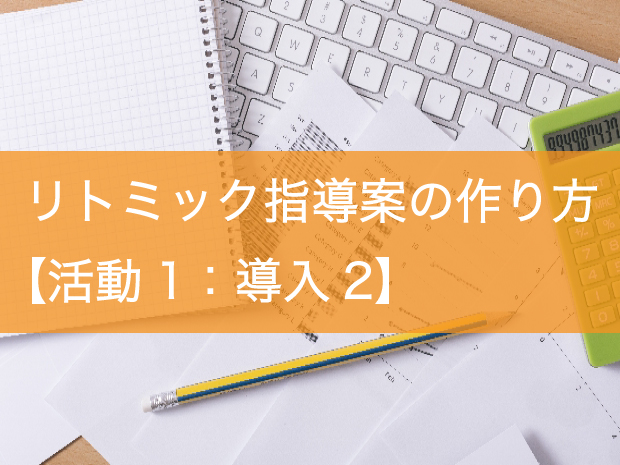
リトミック指導案の作り方、サンプル指導案をもとにご説明いたします。
ここまで、『指導案の組み立て方」の基礎部分についてお話をいたしました。
→リトミック指導案の作り方 その1 【スムーズな活動にするための全体構成の仕方】
「やってみよう」を引き出すために一つレベルの上がる活動を行う
前回の内容は「緊張をほぐす」ということがポイントになっていました。
と同時に「音を鳴らす~止める」といった活動の基礎部分も経験させていくことになっています。
そして何より大事なのは子ども達が活動に対して興味を持てることでした。
やっていることは単純に「先生のものまねをしていく」といった内容でしたが、今回はそれを一歩進めた形の活動になります。
【タンバリンに合わせてクラップさせる】という活動では、指導者は楽器を用いて、子ども達は何も持たず手を鳴らすことになります。
動作は似ているものの、子ども達はそっくりそのまま真似をすればよい、とはいきません。
提示されたルールを自分で判断して動いていくことになるので、ひとつ前の活動よりレベルが上がったことに臨むことになります。
本当に些細な、小さなことなのですがこのように段階を経て難易度を上げ下げするような指導案の流れが子ども達の興味集中を持続させることにつながっていきます。
タンバリンを取り出す行動自体が子どもの興味を集める「お得な場面」になり得る!
ひとつ前の活動では何も使っていませんでしたが、今回の場面ではタンバリンを使います。
ここで「じゃあ、次は~(取り出して見せて)これを使います」というようにアッサリとタンバリンを出してしまうのはもったいないです。
「次は~何を使うでしょう!?」と言いながら背中の後ろに隠して、チラッチラッと見せます。
そうして、子どもの興味を煽り「正解はこれでした!」と取り出して見せるようなクイズ形式にすることができます。
こうした時間はとても無駄に思えるかもしれません。「ぜんぜんリトミック関係ないじゃない!」とも思えます。
でも、子ども達を相手にする場合こうした「遊びの雰囲気」を出していかないと「やらされてる感」が満載で義務でしかない退屈なレッスンになってしまいます。
子ども達はそうした空気をすばやく感じます。
「やらされている=つまんない」となった子どもより「やってみたい=おもしろい!」といった意欲的な子ども、どちらが活動に熱心になるでしょう?
このやりとりは時間にして数十秒のものです。
導入は次の活動への布石を打つこと、子ども達に見通しを持たせることが重要
活動自体は、
- 指導者はタンバリンを一定の拍でならす
- 子ども達は音に合わせてクラップする
といったものです。
これらは、「音を聴く」「反応して動く」といった今後の活動のベース構造になっています。
いきなり【導入1】を飛ばしてここからでも良いのですが、初回ということもあり丁寧に進めています。
- 【導入1】は緊張をなくすこと、【導入2】への布石
- 【導入2】は今後の活動への布石、そして活動の基本構造を経験させる
といった段階になっています。
ここまでを経てようやっと「音に合わせて動く~止まる」という基本を経験させたことになります。
とはいえ、これをやったからといってこの後の活動がスムーズにいくわけではありません。
でも、基本構造である「動く~止まる」を経験したことによって「さっきみたいに止まればいいのかな?」と
いきなりメインの活動に入っても、子ども達は混乱するかもしれません。
でも、導入部分から緊張を解きつつ、内容は活動への布石となるものを行い「見通し」をつけさせることで大きく様子が変わってきます。
指導案作成にあたり、
リトミック指導案作成に役立つ本
| おすすめ本 | 詳細 |
|---|---|
 |
リトミック教育のための原理と指針 ダルクローズのリトミック リトミックの理論やアプローチ方などわかりやすく解説された名著です! |
 |
リトミック論文集 リズムと音楽と教育 エミールジャック=ダルクローズ ダルクローズの論文集。難解な本ですが、読めば読むほど彼の想いや意図が身に染みます。 |
 |
子供を動かす法則 (教育新書 41) リトミックの本ではありませんが、子どもに教えるために必要な技術が網羅されています。リトミック指導者こそ読んでおくべき必読書。 |
