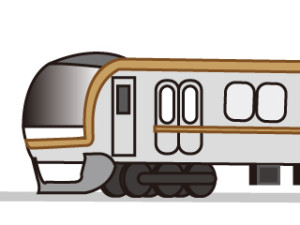誰でも手軽に活動できる!
活動のアウトライン
【活動1.♪はじめよう、の歌に合わせて手を鳴らす】
【活動2.タンバリンに合わせてクラップする、合図に反応する】
【活動3.音楽に反応して動く】
活動ペースの目安
【活動1】〜1分
【活動2】〜2分
【活動3 発展1.2.3】〜7分
活動
【活動1. ♪はじまりのうた、をうたう】
【活動2.タンバリンに合わせてクラップ、合図に反応する】
前回同様のものです。活動2は、タンバリンの「音の強弱やテンポを変える」という変化を入れてもよいでしょう。
【活動3.音楽に反応して動く】
前回では鍵盤ハーモニカで「メロディ」を鳴らしていく活動を行いました。そして、そのメロディを組み替えていくことで「即興的に」音楽をコントロールしていけるものでもありました。
今回は「和音」での演奏で同様に「即興的」な演奏にしていく方法になります。同時に、和音進行の初歩的な事柄を含んでいますので、前回同様「即興演奏」の入り口になると思います。
活動内容自体は、これまでと大差ありません。しかし、「物」を使って行います。それなので、指導方法について多少の技術が求められます。また、絵など視覚教材が少ない分、指導の難易度がこれまでとは異なり上がっているかと思います。
1.絵を見せる
↓以下クリックでpdfファイルが開きます
1-1
【絵1 電車】を使います。提示方法は前回までを参考にして、「すぐに出さない」方法で提示していきましょう。導入部分となるこの場面では、いかに子どもの興味を引き出すか?がポイントになります。
1-2
【絵1 電車】を見せたら、今回の活動を説明していきます。内容としては、
・電車になって動く
・駅では止まる
・合図で掃除をする
というもので、「おそうじ電車」と言えば大雑把なイメージは伝わるでしょう。
2.動きの提示、活動
「おそうじ電車になります。」と用意しておいた布を出してみせましょう。
※ここでいう「布」とは、いわゆるスカーフなどを指します。スカーフがない場合は、50cm×50cm程度の布やハンカチなどで代用してください。
両手で布を持ち、前に出した状態で「電車はこうやって走ります。」と伝えます。表現遊び、とするならば布を使って色々な形をしてみるのも面白いです。とはいえ、今回は活動の最初ということもあるので「ルールを理解する」ことを目的にし、あえて形については全員同じにしています。
2-1
子ども達を部屋の端に座らせ、まずはこちらが動いて示します。「走る」というと子どもは全速力で走りたくなります。今回の活動では、「合図を聴く」というルールを入れるので、全速力で走られるとそれどころではなくなってしまいます。
「おそうじ電車はゆっくり走ります」と伝え、小走り程度の走りを見せましょう。
「電車はどこに止まる?」と走りながら質問してみます。「駅!」という答えが得られるはずです。「そうです、電車は駅に…止まります」と少しスピードを下げながら停止してみせます。
ここまでのルールは、
・布をもって「おそうじ電車」になる
・小走りで動く
・駅で止まる
です。
2-2
実際に、子ども達もやってみる番です。布の配布になるのですが、もし集団の人数が10人以下ぐらいであれば、こちらが直接手渡しをしても大丈夫です。
もし10人以上であれば、箱やカゴに入れて「取りに来て下さい」とする方がよいです。そうでないと、全員に行き渡るまでに時間がかかってしまうため、最初に布を受け取った子から集団が崩れてきてしまいます。布を受け取った子どもは、まず興奮して振ったりかぶったりと賑やかになるからです。
また、なるべく箱やカゴは2~3個用意して、それぞれ離して設置するようにします。一個だけだと、そこにわーっと集中するためトラブルが必ず起きてしまいます。
全員が布を持ったら、「じゃあ、電車になってみよう。出発します」と伝え、演奏を始めましょう。
初回は「走る」「駅で止まる」だけで十分です。余裕があれば【発展1】まで行います。
そして、活動の終わりは布を回収します。手渡しをしていたら直接受け取って、箱やカゴで渡していたら「布を戻します、…」と伝え「…布を返したら座りましょう」と行動の終わりまでを示します。そうすることで次の活動へ移りやすくなります。
3.演奏の仕方
↓以下クリックでpdfファイルが開きます
3-1
今回は複数の音を同時に鳴らす「和音」での演奏になります。青色の数字は指番号です。1は親指、2は人差し指、3は中指、4は薬指、5は小指です。まずは、この8小節を演奏できるようにします。
1小節目から2小節目に移る時、和音が変わっています。その際、鍵盤の押さえ方は変わっていますが共通している(つまり変わっていない音)音があります。これを意識しておくと、押さえ方が変わっても焦ることは少なくなるはずです。
演奏を始める際、いきなりのテンポで始めるよりも、1小節めをゆっくり始めて「だんだん早く」していき2小節目から通常のテンポになるようにすると電車の雰囲気がでます。
3-2
音を止める場所ですが、☆の部分で止めると音楽的にも「終わった!」と感じられるはずです。また、止めるにあたってぶつ切りで止めるよりも、前の小節からだんだん遅くしていって止める方が電車の雰囲気が出ます。慣れないうちは8小節目で止めることを目指して練習してみてください。だんだん遅くしていくコツが身についてきたら4小節目でも止めてみましょう。
ちなみに、なぜ☆の部分で止めると「終わった!」と感じられるのでしょうか?それは和音進行の力によるものです。☆の前の小節は必ず「シレソ」の和音になっています。この曲はハ長調なのですが、ハ長調においては「シレソ」の和音が「緊張」を感じさせる役割になるのです。
そして止まる☆部分は「ドミソ」の和音、これが「シレソ」の後にくることによって「弛緩」「帰ってきた」「落ち着いた」と感じられるようになっているのです。
つまり、「シレソ」のあとに「ドミソ」を入れれば曲をきれいに終わらせられるのです。
もし、慣れてきたら上記譜面にある3つの和音「ドミソ」「ドファラ」「シレソ」を自由に配置して演奏して遊んでみましょう。そうして、終わらせる時は「シレソ」→「ドミソ」とするのです。これが思い通りに出来るようになると、それはもう立派な即興演奏です。
4.発展
4-1
発展1と2を行う際は、2.動きの提示の時のようにこちらが動いて示す必要があります。その際、子どもは布を手にしていない状態にしておく必要があります。なぜなら、子どもは手に物を持っていると、集中が全て物にいってしまうからです。一度回収するなどしましょう。
【発展1】合図1で床を布で掃除する
→動きとしては、しゃがんで床に向けて布を振る動作が簡単です。
【発展2】合図2で上を掃除する(駅の屋根、といったイメージ)
→背伸びして天井に向かって布を振る動作。
【発展3】テンポの変化も入れる
演奏することに慣れてきたら、こういった事も可能になります。ゆっくりになったり、速めになったり。
ここまでで、音の高低の変化や速度に合わせていく、といったリトミック的な目標が含まれていることになります。
また、活動全体の発展例としては、
・「走る」「止まる」
・「走る」「止まる」「合図1」
・「走る」「止まる」「合図1」「合図2」
と複合させていくと、調度良い難易度の上がり方になります。
今回と前回で使用した曲ですが、鳴らし方が「メロディ」なのか「和音」なのか、という違いだけで実は同じような事をやっています。それなので、両方を組み合わせて曲にしていくことも可能です。
また、ハ長調だけでなくト長調やヘ長調でも弾けるようにすれば、音楽の雰囲気が拡がっていきます。
そして、活動内容も実は「イメージ」となるものが違うだけで毎回「動く」「止まる」と同じような事を行っています。
結局同じことなのですが、題材を変えたり、音楽のルールを組み替えたり、物を使ったりするだけで様々な活動にしていくことができます。
こうした「活動」は、いかに「引き出し」があるかでバリエーションのある活動にしていくことができます。ここまでで紹介したものを自由に組み替えて遊んでみて、ご自身のものにしていくと、子どもと活動で「遊んで」いくことがもっと楽しくなるはずです。
| おすすめ楽器 | 商品名 |
|---|---|
 |
AlaMoana アラモアナ ウクレレ 教則DVD付き6点セット ギアペグ仕様 UK-100G/CS |
 |
SUZUKI スズキ 鍵盤ハーモニカ メロディオン アルト M-37C |
 |
キクタニ 皮付きタンブリン 21㎝ TMB-21 |