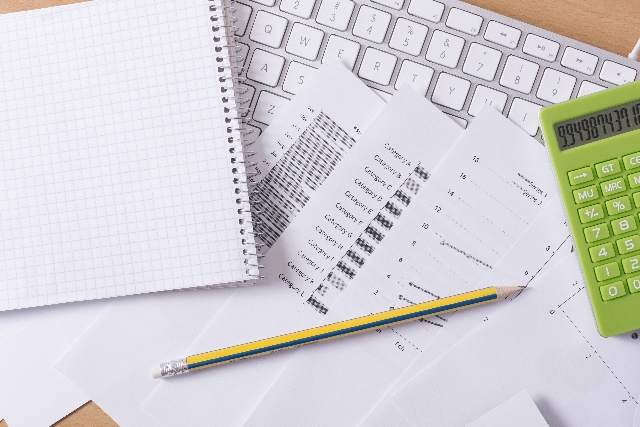
リトミック指導案の作成は「全体の流れ」を意識して組み立てていくと作りやすい
→前回”リトミック指導案の作り方 その0〜指導案を作るために必要なものとは?
この回では、リトミック指導案を作る際に注意する点をお伝えします。
活動は、ただ並べるだけでは上手くいきません。子どもを相手にする上で原則的なルールがあります。
もちろん、子どもは一人ひとり違うので完璧に誰にでも当てはまるとは言い切れません。
ただ、私の経験上ほとんどの現場で適用でき、いつの年代でも有効だった事柄です。
この原則的なルールを全体の流れに組み込めば、スムーズに進められる指導案を作ることが出来るはずです。
原則その1″子どもの集中は短いので一個の活動は短く設定する”
子どもの集中時間はとても短いです。一つの活動をこちらが提示している時が最も興味を持っている時で、集中も生まれます。
しかし、活動が始まると集中は下がっていきます。そして、同じようなことを長時間続けることは難しいです。
スムーズに全ての活動をこなすためには、この集中をなるべく維持させながら進めていかなければいけません。
それなので、一つの活動にかける時間は短く設定して、興味を惹き続けられるよう次々に新しい活動を展開させていく必要があります。
一個の活動時間ですが、年齢が低いほど短く設定します。3歳児であれば長くて5分くらいでしょう。
3歳児を対象に全体で30分の活動だとすると、5分の小活動を6個用意するイメージです。
これに、全体の目標を設定して、いかに各活動へ配分していくかを考えていきます。
原則その2″対象年齢が低いほど毎回内容を大きく変えない”
上記の続きで3歳児対象で小活動を6個用意するとします。
その日の活動全体に対する目標全てを6個全部に当てはめてはいけません。
全体目標に対応する新規の活動は1〜2個に、残りはいつもと同じ活動にします。
毎回毎回、全て新しい活動を行っていくというのは子どもからすると「ついていかなければいけない」といったような負担になる場合があります。
新しい活動というのは、「どんなことするんだろう?」という気持ちになりますが、それは子どもによって「期待」にもなるかもしれないし「不安」にもなるかもしれません。
反対に、いつもと同じ活動というのは「これ知ってる!前にやったやつだ!」と見通しが持てることで、安心と自信が生まれ、それが興味集中を生むきっかけにもなります。
また、一回の活動で物事を身につける、ということは出来ません。繰り返す事で身につけていきます。
それなので、
因みに、私は3歳児が活動の基本になると考えています。
例えば、3歳児の指導案構成が、小活動6個(うち新規活動が1〜2個)、一つの活動が5分だとすると、
- 5歳児では小活動4個(うち新規活動1個)、新規活動15分で通常活動は5分
- 2歳児では小活動6個(うち新規活動1個)、各活動時間は3分(なので全体で約20分)
というように、3歳児案から新規活動数や活動時間を増減させて構成を考えていくことができます。
原則その3″導入から終結までの流れは真ん中にピークを持ってくる”
全体の流れについてです。一つの活動単位での話と同じで、やはり集中は時間が過ぎるほど下がってきます。
では、活動のメインとなるものは、元気な内の最初に行うべきか?と言うと実はそうではありません。
全体の活動の流れは時系列で大きく3つの部分に分かれます。
- 発散させる部分
- 集中させる部分
- 解放する、終結させる部分
1の段階はリトミック活動が始まって5分〜10分くらいの部分です。
この段階は元気があり過ぎて注意散漫になっていることが多いです。
なので、慣れた活動で身体を動かし体力を多少使うような活動がよいです。
ある程度動いて発散したら本題に入る形で2の段階へ移るイメージです。ここで新規の活動などが入ります。
頑張った後は、簡単で楽しいゲーム的な活動で遊んで終わりへ向かいます。これが3の段階です。
ただ、この流れは常に適用できるとは限りません。
活動に慣れないうちは、もしかすると1の段階がメインになるかもしれません。
また、こちらの目標としている2の段階にこだわりすぎると「やらせてる感」が強くなり、活動が楽しいものではなくなってしまいます。
指導案”例”の公開
ここまでの原則を踏まえると、
- 全体の目標を決定、内容を検討する
- 細かい活動を多く用意する
- 新規活動は真ん中に、慣れた活動を前後に入れる
といった形で指導案を構成していくことになります。
とはいえ、これら文字だけの説明では分かりにくいかと思います。
それなので、今度から実際に作成した指導案で一つ一つ流れをご説明していきたいと思います。
この指導案ですが、
- 対象は3歳児10人の集団
- 活動時間は30分
- 初めてリトミックを行う
といった設定です。
次回は導入部分についてお伝えします。
リトミック指導案作成に役立つ本
| おすすめ本 | 詳細 |
|---|---|
 |
リトミック教育のための原理と指針 ダルクローズのリトミック リトミックの理論やアプローチ方などわかりやすく解説された名著です! |
 |
リトミック論文集 リズムと音楽と教育 エミールジャック=ダルクローズ ダルクローズの論文集。難解な本ですが、読めば読むほど彼の想いや意図が身に染みます。 |
 |
子供を動かす法則 (教育新書 41) リトミックの本ではありませんが、子どもに教えるために必要な技術が網羅されています。リトミック指導者こそ読んでおくべき必読書。 |
