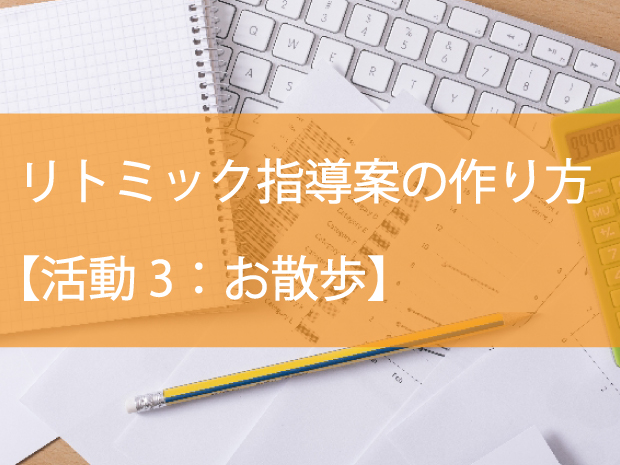
リトミック指導案の作り方、サンプル指導案をもとにご説明いたします。
ここまで、『指導案の組み立て方」の基礎部分についてお話をいたしました。
→リトミック指導案の作り方 その1 【スムーズな活動にするための全体構成の仕方】
定番の「お散歩」といった活動、なぜ行う??
どんな年齢のリトミック活動でも、この「お散歩」のように【歩く】という活動は出てきます(乳児対象の場合は「親子で歩く」というように内容に違いはあります)。
これは、リトミックで満たすべき条件が最大限に得られるから、だと言えます。
例えば、リトミックの大前提として「全身の感覚をもって音楽を感じる、理解する」というものがあります。
活動の中で行われる「歩く」「(音楽が止まったら)止まる」といった内容は一見するととても単純なものです。
しかし、その中には「全身を使う」「聴く」「反応する」「考える」などリトミックで経験していくべき項目がふんだんに盛り込まれています。
また、「お散歩」という事柄は子ども達にとってイメージがしやすいものでもあります。
子どもからすると、「あ、知ってる!」と思えて「これから歩いたりするのかな??」と
そして何より身体を動かすことによって気持ちを発散させることにもなります。
子ども達の集中や興味があるうちに、また身体と気持ちをメイン活動に向けて暖めていく、という意味で前半に行うのがよいでしょう。
立って行う活動は、いきなり行うより段階をつけたほうがスムーズに行いやすい
ここまで、2つの導入活動で「音の有無に反応する」といったことを行ってきました。言ってみれば、これからが本番になります。
5歳児くらいだと、初回の活動で前2つの導入を飛ばしても「お散歩」の活動へ入っていく事は出来ると思います。
しかし、3歳児の集団でそれを行うと「開始早々、走り回る」ということが予想されます。
しかしそれはあくまで「私の経験からのイメージ」です。
集団とは様々な性格、気質の子どもが集まっているものなので一概には「○歳児だからこう」とは言えません。
つまり、5歳児でも、その集団によっては難しいことがあるでしょう。
そもそも、走れる空間のある部屋でじっとしている、ということは子ども達からすると難しいはずです。
そんな状態で「今からお散歩をするよ〜、どうするのかっていうと音楽が鳴ったら〜」なんてルール説明は聞いてもらいにくいです。
それなので、遊びのように導入活動を2回入れていくことで段階をつけていき、「音に反応する、止まる」という最低限のルールをしっかりと定着させていくことをねらいました。
こうすることで、「音楽が止まったら動きも止める」というルールが「さっきの(タンバリンに合わせてクラップする)と同じように…」と伝えやすくなります。
「お散歩」の活動は、ほとんどすべての活動の基礎になり得るので丁寧に行うべき
正直、導入活動を2回入れるのは回りくどいやり方かもしれません。
しかし、この「音楽に合わせて歩く、止まる」といった内容は今後行っていく活動の基礎になります。
リトミックの活動では、歩く以外にも走ったり、ゆっくり動いたり、模倣してみたり、合図や音楽を聴き分けて表現してみたりと様々な事を行います。
それらほとんどすべての内容が「歩く、止まる」の発展系だと言えます。
それなので、このお散歩といった活動は子ども達が慣れるまでは
ちなみに、指導案の中で「音楽が止まったら赤信号→なので止まる」としています。
ここで、子どもの動きとして「止まる際に「あか!」と言って手を挙げる」というものがあります。
これは、ただ止まるだけではなく行動をプラスすることで、より「止まる」という動作に意識を持っていけるように行っています。
今回、具体的な指導の流れは省きますが、以下の記事にあることを意識していくとスムーズに進められるはずです。
→【リトミックの指導方法】分かりやすい提示は「モデルを示す」2
リトミック指導案作成に役立つ本
| おすすめ本 | 詳細 |
|---|---|
 |
リトミック教育のための原理と指針 ダルクローズのリトミック リトミックの理論やアプローチ方などわかりやすく解説された名著です! |
 |
リトミック論文集 リズムと音楽と教育 エミールジャック=ダルクローズ ダルクローズの論文集。難解な本ですが、読めば読むほど彼の想いや意図が身に染みます。 |
 |
子供を動かす法則 (教育新書 41) リトミックの本ではありませんが、子どもに教えるために必要な技術が網羅されています。リトミック指導者こそ読んでおくべき必読書。 |
