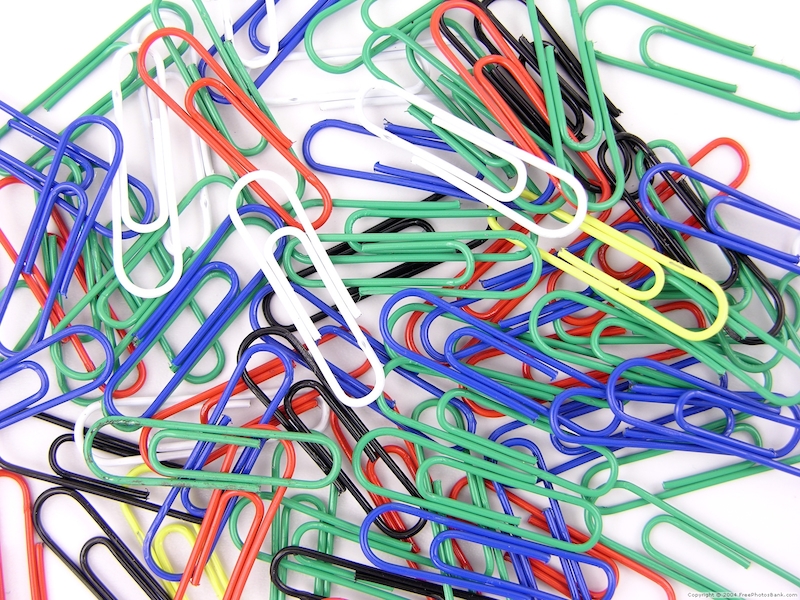「叱る」ときは、その子どもの行動を見極めてから!
活動において、よりスムーズに進めるためのテクニックをご紹介します。
子どもへこちらが「質問」する際の方法
以前の記事にある「じらし」と近いことなのですが、活動で子どもにイメージを持たせる際にクイズ形式で行ったりします。
こうすることによって、子どもは頭で考えることを繰り返すのでイメージを膨らませることに繋がります。
クイズ形式といっても複雑なことではなく、正解に向けて連想していけるようヒントを細かく出していくだけです。
「今日はみんなでこんなところに行ってみたいと思います。」
「乗り物があります」
「レストランもあります」
「観覧車があります」
「ゆ、がつくところです」→正解は「遊園地」
ヒントを少しずつ出していくことで、ああでもないこうでもないと子ども達が考え始めるので、イメージを膨らませることになり、結果その後の活動が豊かなものになります。
そして何より「集中」が生まれます。
注意引きの行動や言動について
注意引きの行動、言動とは言ってしまえば「ふざける」ようなことを言います。
こうした行動にでる子は、こちらを試しているかもしれないし、緊張の裏返しかもしれないし、単に状況をわかっていないだけなのかもしれません。
なんにせよ、こうした行動や言動は活動を進める上で全体へよくない影響を広げかねないので、様子によっては対処する必要があります。
「そういうことは楽しくないよ」という態度を示すために「無視」をして乗らないのが一つの手です。
こちらの反応を楽しんでいるだけの子に有効です。
ただし、何でも無視するのではなく、その子の別の場面では褒めたり関わってみたりします。
特定の行動には「乗らないよ」と態度で示すのです。
時には「叱る」ことも必要です。線引として「迷惑をかける行為に対して」とするのがよいでしょう。
例えば、活動中にピアノに触れにくる子がいたとします。
大抵の子は、そういった行為に対し(きつい言い方ですが)睨みを利かせると「あっ、まずかったかな…」と繰り返しはしません。
しかし、そうした大人(相手)の様子に気づきにくい子はそれを楽しい遊びの関わりと勘違いをして2度3度と繰り返します。
いざ「叱る」際は途中で演奏を中断して、その子の目の前まで行き、しゃがんで目線を合わせます。
そして、こちらとしては十分迷惑なこと、みんなにも迷惑なことを「気持ち」として「そういうの、嬉しくありません。
先生は嫌です。やめてください」としっかり伝えます。
叱る、からといって大声をだすような「怒鳴る」わけではありません。
あとは、注意引きの言動として「チンチン」「うんち」「おしっこ」といったことを発する子がいます。もう、子ども達の大好きな言葉です。
そうした言動については、わざと大きな声で「えっ!チンチン(うんち)!?なに、トイレに行きたいの!?早く行っておいで!!」と言えば「イヤ、そういうつもりじゃ…」と言わなくなります。
「なーんだ、◯◯くん(ちゃん)赤ちゃんみたいになっちゃたのかと思ったヨ!」と雰囲気を険悪にしないようおどけてみせつつ、暗に「もう言うなよ」という意味で念押しすれば十分です。
グループの分け方
活動によってはグループなどの小集団にわけることもあります。そうした時の分け方についてです。
4歳児以上であれば、どんな方法でもある程度問題なく行えると思います。
しかし、3歳児では難しい場合もあるかもしれません。
「絶対に○○と一緒じゃないとやだ!」と相手にこだわったり、グループという概念自体を理解することが難しい子がいたりします(この様子は4歳児以上でも見られたりはします)。
とはいえ、3歳児は「特定の友達と一緒に」ということを意識し始めるころなので、まだ小集団ではなく全員で活動していく方がよかったりもします。
最も簡単な2グループの作り方
全員で行うには人数が多すぎる、かといってしっかりグループに分けるにはタイミングではない、という時に便利な方法です。
「男の子はこっち(場所を示して)、女の子はこっちに行って座ってください」というように男女で分かれるのが最も簡単で確実な方法です。
欠点は、その集団の男女比によって均等ではない2グループになる、ということです。
頭を触られたら…
3グループ以上に分ける際に有効な方法です。
「目をつぶってください。今から先生が頭をポンと触ります。」といい最初のグループの子を選んでいきます。
目をつぶらせることで子どもは集中し、落ち着いてグループ分けをすることが出来ます。
予め全員の人数からグループ数で割った数を認識しておく必要があります。
また、この分け方の利点として、グループのメンバーをこちらがコントロールできるところにあります。
クラスには、いい意味でも悪い意味でも「ムードメーカー」となる子が数人はいます。
そして、そうした子達はいつも固まっている傾向があるので見分けやすいです。
それなので、その子達を一緒にせずバランスのよいグループに振り分けることがやりやすくなります。
クラスのグループで分ける
園では、そのクラス内でグループが決められていたりします。
そうしたグループをそのままリトミック内でも適用させる方法もあります。
そうしたグループは大抵、担任の先生が熟考した結果のメンバーの配置となっているので、そのまま活動へも活かせます。
欠点として、そのグループ数がこちらの希望する数と一致しない場合があることがあります。
また、欠席している子が特定のグループに集中していると、グループ人数に偏りがでることがあります。
環境を利用する
例えば、クラスにある「イス」ですが、落ち着きの少ないクラスの子ども達を集める際に有効だったりします。
予め壁際にイスを並べておけば「座って先生の話を聞く番」という流れが「じゃあ、座ってください」の一言で乗せやすくなります。
机は基本的に「潜らないように」しておくことが大切ですが(過去記事参照)、使いようによっては「トンネル」として使用できます。例えば、「この音楽の時はトンネルを通ってね」とか…。
柱や壁、棚などにある「色」が活動に活かせたりします。
グループを分けた際に、グループ名を「赤グループ」として赤色がある壁のしたに場所を示したりできます。
園帽子は、特定の役割を持たせる場合に使えます。
帽子をかぶっている人は◯◯の役、というようにすれば視覚的にもわかりやすくなります。
全ての技術は対象を見極めて使う
これまで【指導方法】としてさまざまな技術を紹介してきましたが、これらは私自身が経験で得たものや本で学んだものを総合したものです。
そして、全ての現場で活用している原則的なものです。
しかし、全ての現場で活用出来ているのは、全ての現場で活用してきた経験のある私だから出来るのであって、誰もがマニュアル通りに進められるものではないと思っています。
それなので、もしこれらを参考にされる場合は、ご自身の現場では有効なのか?と試すつもりで行って頂きたく思います。
人間を相手にする以上、完璧な正解はありません。正解は、現場を受け持つご自身が見つけ出すものです。
とはいえ、これらを知っていれば活動を進めることがいくらか楽になることは間違いないと思います。
なぜなら、私が苦労して導き出した方法でもあるので、実践済みという裏付けが’あるからです(1年目で四苦八苦していた自分に教えてやりたいです)。
ブログを御覧になられている皆様のお役に立てれば幸いです。
| おすすめ本 | 詳細 |
|---|---|
 |
リトミック教育のための原理と指針 ダルクローズのリトミック リトミックの理論やアプローチ方などわかりやすく解説された名著です! |
 |
リトミック論文集 リズムと音楽と教育 エミールジャック=ダルクローズ ダルクローズの論文集。難解な本ですが、読めば読むほど彼の想いや意図が身に染みます。 |
 |
子供を動かす法則 (教育新書 41) リトミックの本ではありませんが、子どもに教えるために必要な技術が網羅されています。リトミック指導者こそ読んでおくべき必読書。 |
 |
人を動かす 新装版 「指導する」ということにおいて重要な人との関わり方がわかる本です |
 |
障がいのある子との遊びサポートブック―達人の技から学ぶ楽しいコミュニケーション この本に網羅されている技術は子どもと接する上で欠かせないものになります |