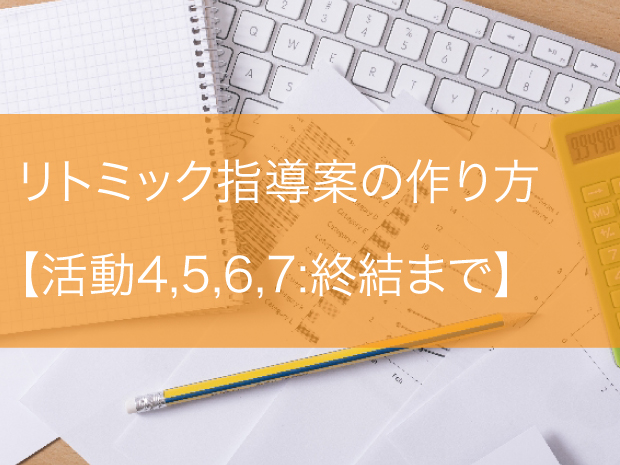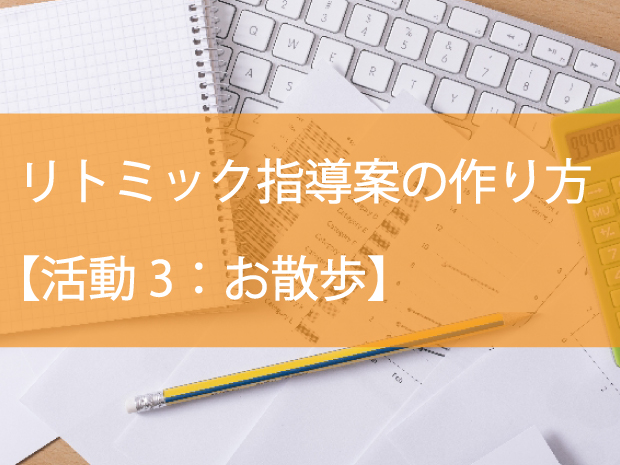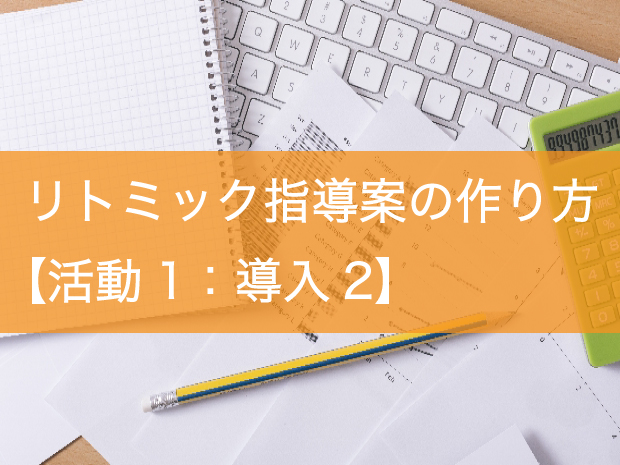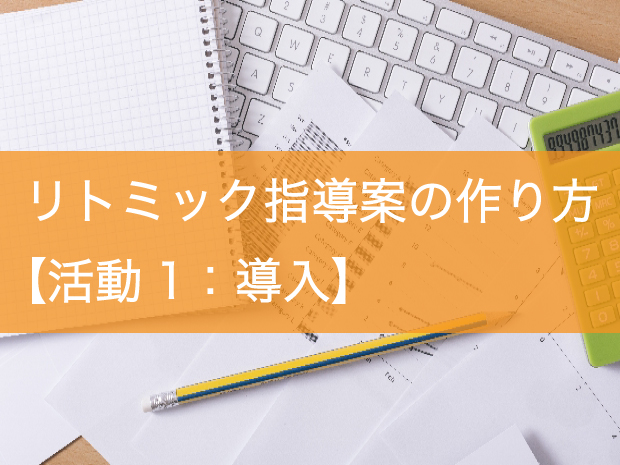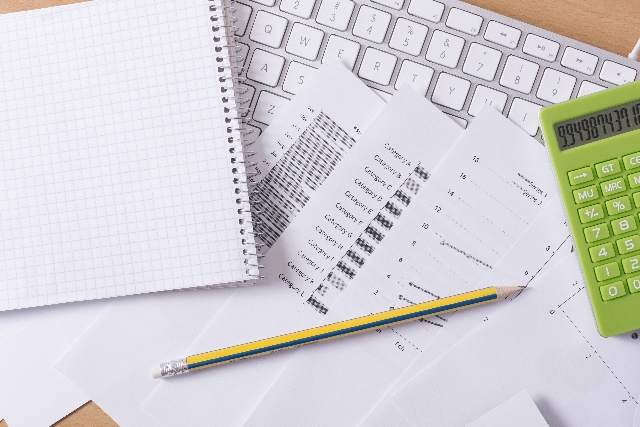リトミック指導案の作り方、サンプル指導案をもとにご説明いたします。
ここまで、『指導案の組み立て方」の導入から最初の活動までについてお話をいたしました。
→リトミック指導案の作り方 その1 【スムーズな活動にするための全体構成の仕方】
集中を要する「音を聴き分ける」という活動
さて、以前の記事で活動の真ん中にピークを持ってくるという事をお伝えしました。
全体の活動の流れは時系列で大きく3つの部分に分かれます。
- 発散させる部分
- 集中させる部分
- 解放する、終結させる部分
前回の「お散歩」が1だとしたら、次からの活動が2になります。
それなので、ここからが指導案で立てた「目標」の部分になっていきます。
「お散歩」ではリトミック活動で行う「動く」「止まる」という基礎部分を遊びながら行いました。と同時にこれらは以降の活動の『前提条件』になります。
この後の活動ではテンポや音楽の違い、合図に反応をしていくことになるのですが、そもそも「音を聴く(自分から能動的に、という意味で)」ことが出来ていないと活動は成り立ちません(ただ好き勝手に走り回る、になってしまいますよね!?)。
「導入」でこれからはじまる活動への示唆、体験を。
「お散歩」でルールの経験と、遊びたい!といった有り余る欲求の発散を。
ある程度遊べたら、「次はこういうはどう??」というように次の遊び(活動)を提示する。そんな流れになります。
本当に「聴く」ということが要求される車のイメージ活動
「車に乗る=走る」というイメージ活動です。今度は歩くことよりも激しい身体の動きをするので子ども達にとっては刺激的なものになります。
刺激的、ということは子ども達からすると「走る」ことのみに夢中になりやすいです。
しかし、その状態でも「音楽を聴く、反応する」ということを行うことになるので自分をコントロールしていかなければいけません。
そんな状態だからこそ集中することが培われていく、と言えるでしょう。
また、一つ前の「お散歩」の活動で出てきた「赤信号=止まる」という概念もそのまま活かせます。
それなので、イメージが日常的であり連想しやすいことから「お散歩」から「車」の活動はスムーズに移行し易いです。
さて、この活動の入り方ですが年齢が低いほどしっかりイメージを持たせることが大切になってきます。
そうしないと、ただワーッと始まり走り回ってお終い、といった経験にしかなりません。
「お散歩」の活動が終わったら一度、子ども達を座らせて以下のように進めるとよいです。
「次は…乗り物に乗りたいと思います。」
「(ハンドルを持つふりをしながら)こういうふうに…運転する乗り物って知ってる??」
「そう!今度は車に乗ってみます。…乗ってみたい子!じゃあ、みんなに鍵を渡すね(一人ひとりに渡すふり、余裕がなければいっぺんに渡すふり)」
「じゃあ、みんな鍵を開けて〜、乗ります(よーいしょ)、ドアを締めて(カチャン!)、エンジンかけて(ブルーン!)」
この段階まで来たら「まだ赤信号だから止まっててね…青になったら走るよ…」と小声で伝えつつ準備をさせます。
音楽が始まったら一斉に走り出すでしょう。
もし、人数が多いクラスの場合は「お友達とぶつかるとケガになるからね、離れて一人で走ってね」と声掛けをしておくようにします。
音楽を「聴き分ける」という動物のイメージ活動
続いての活動は2種類の音楽を「聴き分ける」という活動になります。
これまで「歩く」または「走る」と「止まる」という二つの動きだった内容が一段階、高度になります。
最初に絵を見せてイメージさせることを行いますが、これには2つの目的があります。
一つは、具体的であり子ども達もよく知っているであろう動物をイメージさせることで、「どんなふうに動けばいいのか」という活動へのヒントを与えることになります。
そしてもう一つの目的として「休憩」があります。
この一つ前の活動は「走る」ことをメインに行ったので、子ども達は充実感とともに疲れも伴います。
活動も中盤に差し掛かっていることもあるので、この辺りで休みを入れたほうが後半へのためになります。
それなので、ただ絵を見せるのではなく、紙芝居のようにしたりクイズコーナーのようにしたりと工夫して2〜3分かけて休みつつ、でも次への期待に繋がるような時間にしていきます。
参考:【リトミックの指導方法】物を使った活動での提示の仕方1
また、ここでは動物の動きをイメージさせていますが、必ずしも「ゾウなら手を前に伸ばして鼻のつもりでパオーン」といった特定の動きをさせる必要はありません。
あくまで「音楽の違い」を動きとリンクさせてイメージできるように動物を提示しています。
指導案の「指導ポイント」では「鳴らしながら動き見せる」としました。これは、タンバリンで音楽の拍を鳴らしながら動きを見せることを想定しています。
この時点では指導者は両手が塞がっているため、特定の振り付けのようなものは提示されていません。音と「下半身の動き」のみです。
こういった、子ども達がよく知っている事柄をイメージ活動で使う場合は、最低限のルールのみ伝えて、あとは自由にさせていくと面白いです。
活動を進めながら「わー!◯◯くんのゾウさん、すごい◯◯だね!」「みんな見て見て◯◯ちゃんのことり、とても◯◯だよ!」など、個人の良いところ、独創的なところなどを周りとシェアしていける機会が生まれます。
そのことで、活動が盛り上がったりします。
参考:【リトミックの指導方法】分かりやすい提示は「モデルを示す」3
指導案では「ゾウ」と「ことり」としていますが、この限りではありません。
自由に変えても良いと思います。
最後に「遊び」とちょっとした「スリル」のある活動を
ここまで来たら、活動は終結に向かいます。どのように終結させるかで、子ども達は「また遊びたい!」となるか「もういい」になるかが分かれます。
メインである「音楽を聴き分ける活動」が終わったら、子ども達は頭も身体もクタクタになりつつあります。この段階で課題めいたものを行うと「また!?もうこういうのはやりたくない!!」となってしまいます。
疲れた印象だけ残ってしまい「リトミック=やりたくない」という図式になりかねません。
それなので、最後に行う活動としては「激しくないもの」「頭を使わずにできるもの」「でも、楽しいもの」という条件をもった活動が最適です。「お化けの森活動」はこれにピッタリです。
活動としては単純で、不安な音楽の中、子ども達は抜き足差し足忍び足…合図がなったらその場でしゃがんで隠れる(ふりをする)、これだけです。(ちなみに終わらせ方は、「森を抜けた!」で明るい音楽とともにスキップします)
もし、時間と子ども達に余裕があるのであれば二つ前の活動「車」をもう一度入れてもよいでしょう。
先ほど行ったものなので、負担なく取り掛かれるはずです。ただし疲れているので活動時間は最初より短くします。
「走る」ことも「楽しい!」につながるので、「あー面白かった!」と活動を締めくくれるでしょう。
最後に「終わりのうた」で活動はおしまい。歌うことで「これで今日はおしまい」「いつもの時間に戻る」という気持ちの切り替えを促します。
色んなことをして考えたり疲れたりもしたけど楽しかった!といった子ども達の反応が得られたら、30分の活動は成功といえるでしょう。
さいごに
リトミック指導案の基本的な流れとしては以上です。
最初の記事では指導案の全体的な流れをお伝えしました。これは活動内容についてではなく、子どもの動きや様子を想定して組まれた流れになります。
私がリトミック指導案で失敗してきたことといえば、このように「流れ」を意図して組めていなかったことが大きい原因でした。
「音の高い低いを理解させるためには…」
「即時反応は大切だからやらなきゃ…」
「今回はギターを使ってみたいから…」
などと、自分の都合を優先させた結果、非常にストレスやプレッシャーのかかる活動になっていたりしました。そんなものでは子ども達は嫌になってしまって当然です。
いかに子ども達を楽しませることができるか?その中で何を経験させるのか?そのためには、どう進めればいいのか?
もちろん、これらはあくまで私自身の経験によるものです。あらゆる子ども達に適したものではありません。現場ごとに吟味していく必要があります。
絶対、という方法はありません。
ただ、一つの「考え方」があると、そこから方法を発展させることが出来るようになってきます。
ここでお伝えしたことが、皆様の「一つの考え方」としてお役に立てれば幸いです。
リトミック指導案作成に役立つ本
| おすすめ本 | 詳細 |
|---|---|
 |
リトミック教育のための原理と指針 ダルクローズのリトミック リトミックの理論やアプローチ方などわかりやすく解説された名著です! |
 |
リトミック論文集 リズムと音楽と教育 エミールジャック=ダルクローズ ダルクローズの論文集。難解な本ですが、読めば読むほど彼の想いや意図が身に染みます。 |
 |
子供を動かす法則 (教育新書 41) リトミックの本ではありませんが、子どもに教えるために必要な技術が網羅されています。リトミック指導者こそ読んでおくべき必読書。 |