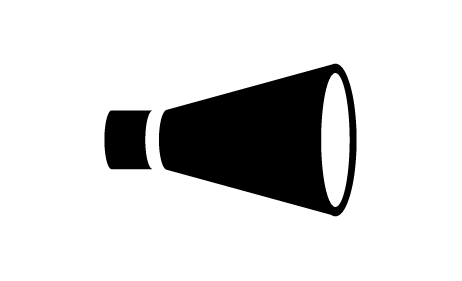全員で!動いても見ていても楽しめる活動になる!!
本日の親子リトミックで、活動の最後にスパークハーフを使った活動をしました。
(スパークハーフについては、以下の過去記事を参照)
集団での遊びに活用出来るスパークハーフ | 子どもと音楽で遊ぶリトミック指導
わりとポピュラーな道具でもあり、リトミックではなくとも、児童館など親子活動の場で見られます。
改めて、この魅力的なモノについて考えてみます。
見て、触れて、感じて楽しい!を「全員」で共有できる
用意している大きさにもよりますが、私の持っているスパークハーフは3m四方くらいのものです。
となると、一人で持って揺らすことは出来ません。
それなので、必然的に大人数人が端を持って揺らすことになるのですが、これが「場」を作り雰囲気を共有することになります。
それぞれの親子が思い思いのことを楽しむ活動も良いですが、活動の終わりにこういった事を行うと、とても雰囲気よく終わることができます。
親子リトミックの活動では、お母さん(お父さん)に周りを持ってもらい、子どもは膝元で見て触って楽しむか、積極的な子は中に入っていって楽しむことになります。
集団でワイワイとやることになるので、少し不安な気持ちになってしまう子も当然います。
その場合は、無理に入ってもらわずに、離れて見ていてもらうようにします。
とにかく、全員で楽しむことが出来る活動です。
どんなことが出来る??
ただ揺らすだけでも十分楽しめるのですが、ここにリトミックの意味付けをするとなると??
例えば、ゆるやかな音楽、激しい音楽に合わせて揺らしてもらうとします。
音楽に合わせて大布が揺れることを「感じる」というだけでも十分、感覚を使って音楽を経験していると言えるでしょう。
年齢にもよりますが、自分で持ってみると、より感じられると思います。
活動を行う注意点として、布の中に子どもが集中すると、ぶつかったりとトラブルが必ず起きます。
それなので、そういった場合はスタッフか、親子で1〜2組ほど一緒に入ってもらうなどして、様子を見ていてもらう必要があります。
揺らすだけではなく、揺らしながら回ってみても面白いです。
まるでメリーゴーラウンドのようになることで、子ども達からして視覚的な変化があり、興味の持続につながります。
たいした重さもないので、持ち運びに困ることはないスパークハーフ。持っていて損はありません。
[cc id=3452]